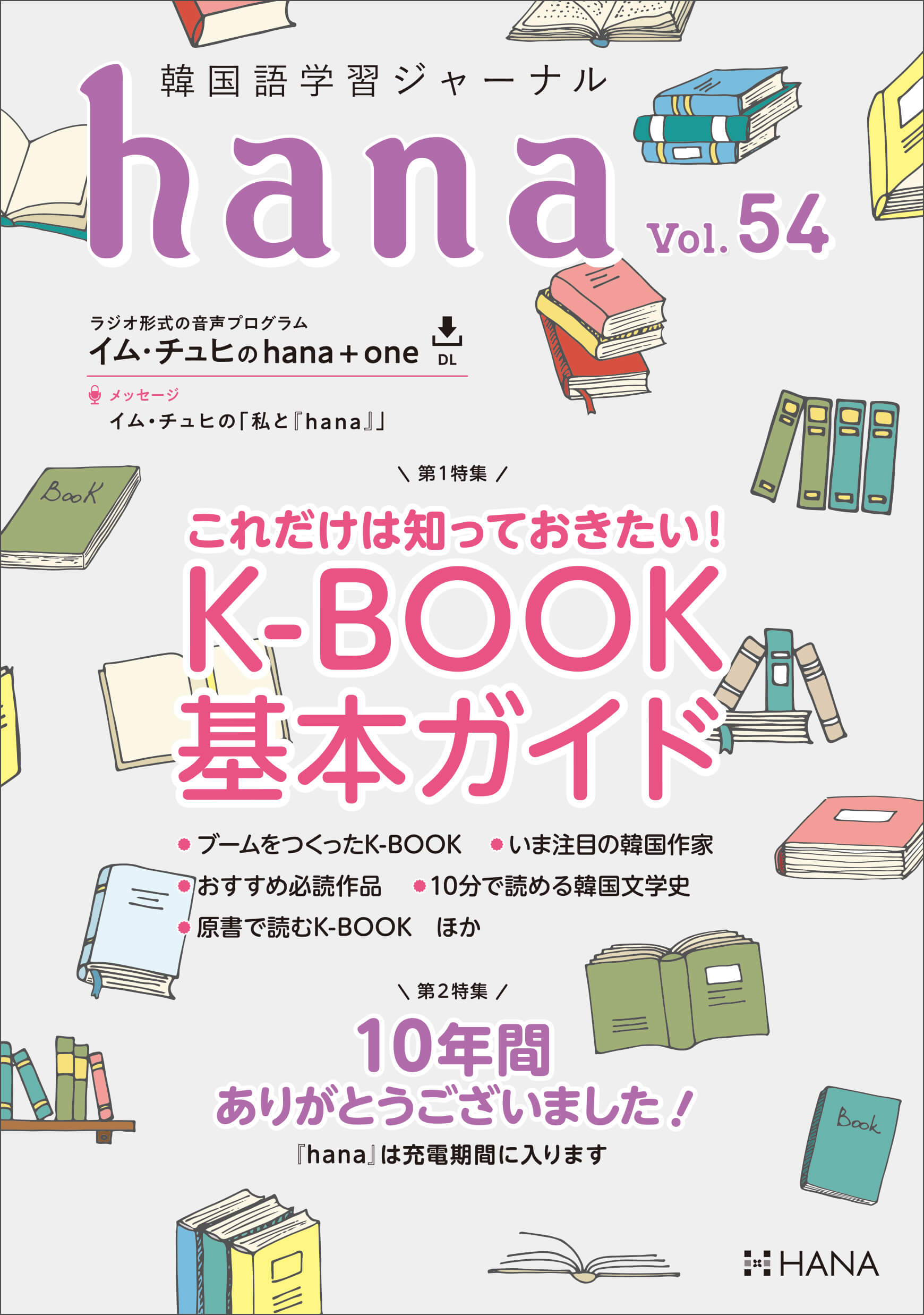この記事では、『韓国語学習ジャーナルhana Vol. 54』辻野裕紀の連載コラム「もうひとつのまなざし」(P.023)の内容を、さらに深掘りした音声コンテンツの内容を掲載しています。ぜひ本誌のコラムと合わせてお楽しみください。
記事の目次
声で楽しむ「もうひとつのまなざし」
皆さん、こんにちは。辻野裕紀です。お元気でお過ごしでしょうか。
前回は「言語学習とウェルビーイング」というタイトルで、ウェルビーイングや幸福、健康、予防医学などといった視座から言語学習を見据えてみました。その中で、言語学習と老後のQOL(クオリティ・オブ・ライフ)についても触れましたが、神経科学の知見などを持ち出さなくとも、言語学習が老境の生活を明るくすることは自明かもしれません。
面唔の機会は一度もなかったものの、著作を通じて多くを学ばせていただいた、言語学者・スラブ語学者の千野栄一先生は「もしつぎつぎに外国語を学ぼうと決心すればいくら日本人の寿命が延びようとも死ぬまで退屈するひまはなく、することのない老年の不安からは永遠に解放されるのである」と書いておられます(『外国語上達法』、千野栄一、岩波書店、pp.206-207)。
学者によって見解は異なりますが、世界にはおよそ6000ぐらいの言語があると言われていますので、たしかに言語学習を趣味にしてしまえば、荏苒と時を過ごすこともなくなるでしょう。韓国語だけでも深く肉薄するには何十年という歳月を要しますし、母語の日本語でさえ一生かけて学び続けるものです。「完璧な母語話者」なるものは原理的に存在し得ません。その意味で、ことばに関心を持ったということは、その時点でもう既にとても幸せなのです。

ジョルジョ・アガンベンの英訳者としても著聞する哲学者のダニエル・ヘラー=ローゼン氏が、ロマン・ヤコブソンの論考を引きながら指摘するように、私たちは母語を獲得するプロセスにおいて、喃語として一時は発音していた無限の音の数々を忘却せねばなりません(『エコラリアス 言語の忘却について』、ダニエル・ヘラー=ローゼン、関口涼子訳、みすず書房、p.12)。
すなわち、母語の習得とは生得的に所有していた潜在的可能性の喪失でもあり、翻って、非母語学習とはその喪失を恢復させる営みです。
そして、それは実存の原点へと回帰していくことでもあって、言詮を絶する生の円環性を体感させてくれます。そうした事実に思いを致すとき、言語というのはなんと奥深いものであろうか、言語学を専門にして本当に良かったと、その幸せを噛みしめたくなります。
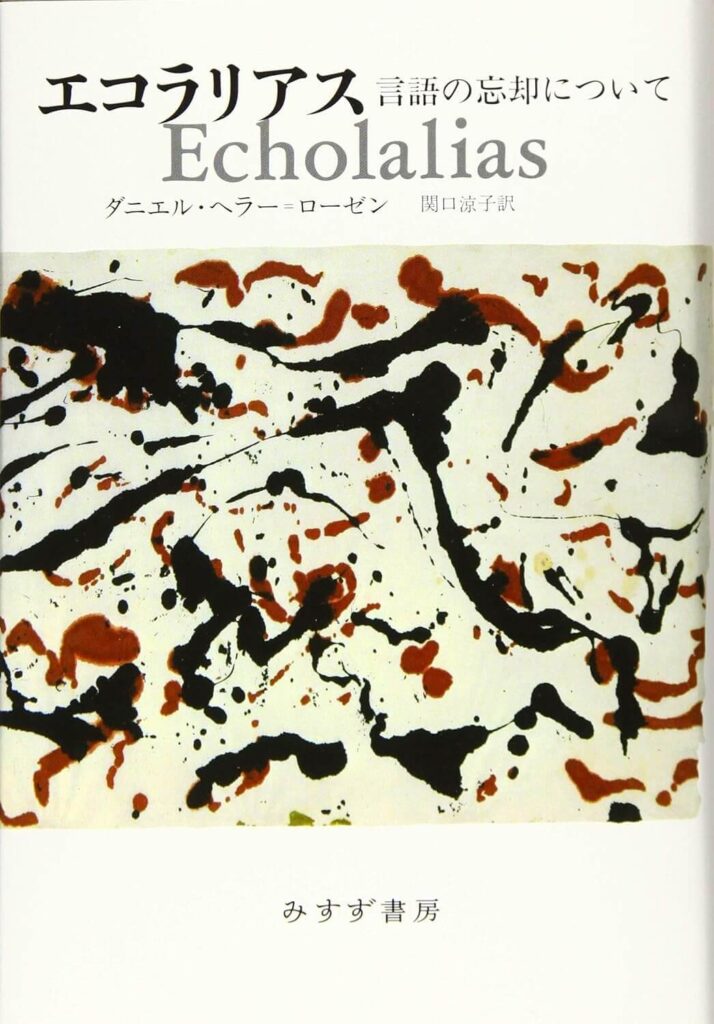
第4回「読書をめぐる断想」
ところで、今回は読書について語ろうと思っていますが、私は子どもの頃から本や書店が大好きで、その延長線上に今の大学教員という仕事があります。中学生の頃、文化人類学者の研究室を訪問する機会があり、汗牛充棟の書物に圧倒されたことをよく覚えています。学者になったら、浩瀚な蔵書に囲まれて、読書三昧の生活が送れる。そんな淡い期待もあって、人文系の学者という道を選びました。
今の私の研究室にも、大量の書籍が所狭しと櫛比していて、「ここにある本、全部読んだのですか?」としばしば聞かれます。もちろん、そんなはずはなく、そもそも持っているのか持っていないのかすら把握していない書物もあります。
買ったはずの本が見つからず再購入したら、その後床にピラミッド状に堆く積み上げられた本の山が崩落してその中から偶然発見されるなどといったことも日常茶飯事です。
弁疏めいてしまいますが、現在の日本の大学は読書だけに集中できるような悠長な場ではなく、また、本が置ける空間的な限界もあるので、致し方ありません。
本とはいつかそれが理解できるような自分になりたいから買うもの
ところで、私が学生たちと接していて驚くのは、「買った本はすぐに読まなければならない」という思い込みが強すぎることです。本とはいつかそれが理解できるような自分になりたいから買うものであって、それは日本語書籍でも韓国語書籍でも同じです。
 辻野裕紀
辻野裕紀そして、「理解できる自分になりたい」と願った時点でその本との関係性は成立していて、実際にそうした自分になれるかどうかは、その書に出合った段階では判じることができません。
いきなり蠅頭の細字と格闘する必要はなく、とりあえず手に入れ、前書きだけでも読めれば十分です。著者や訳者のプロフィールを眺めるだけでもよいでしょう。
このような楽観的で未来志向的な構えでないと読書は愉しくないし、読まねばならないという当為性に根差した読書に魅力はありません。書物を買うとは、いつか分かるかもしれないし、分からないかもしれない、自身の変容可能性のうち、分かるほうの自分に希望を賭してみる、時間性を伴う行為なのです。
昨年易簀された著述家の松岡正剛氏は、「『読書はたいへんな行為だ』とか『崇高な営みだ』などと思いすぎないこと」が大切であり、本は「日々の着るものに近い」「ジーンズの上にシャツを着たりセーターを着たりジャケットを着たりするように、自分のお気にいりのジーンズ・リテラシーの上にいろいろ本の組み合わせを着たり脱いだりすればいい」といった旨のことをおっしゃっています(『多読術』、松岡正剛、筑摩書房、pp.12-13)。
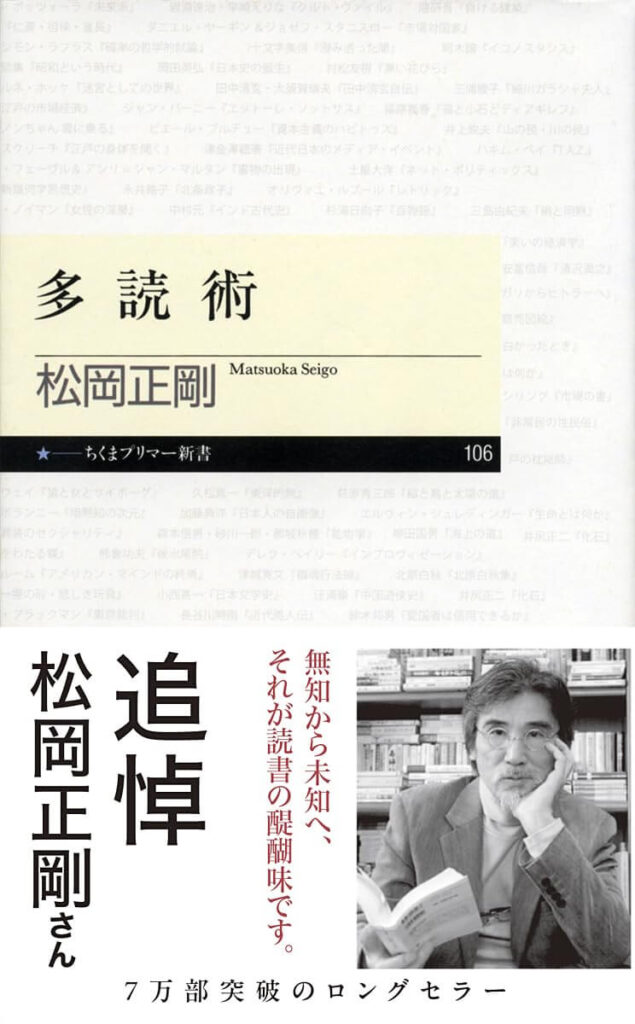
私もかかる読書論には全面的に賛同します。読書という行為を「神聖化」することでかえって本が読めなくなってしまうというのはおそらく多くの人が経験することで、それでは本末転倒だからです。
本とは常に「思考」を要求してくるものであり、それに応えない読書は無意味だ
ショウペンハウエルが「読書は、他人にものを考えてもらうことである」と道破したのはよく知られています。
「本を読む我々は、他人の考えた過程を反復的にたどるにすぎない」「精神も、他人の思想によって絶えず圧迫されると、弾力を失う」などとも叙しており、多読を否定的に捉えつつ、「熟慮を重ねることによってのみ、読まれたものは、真に読者のものとなる」として、自分の頭で考えることの重要性を説いています(『読書について 他二篇』、ショウペンハウエル、斎藤忍随訳、岩波書店、pp.127-129)。
このことは言い換えると、本とは常に「思考」を要求してくるものであり、それに応えない読書は無意味だということです。
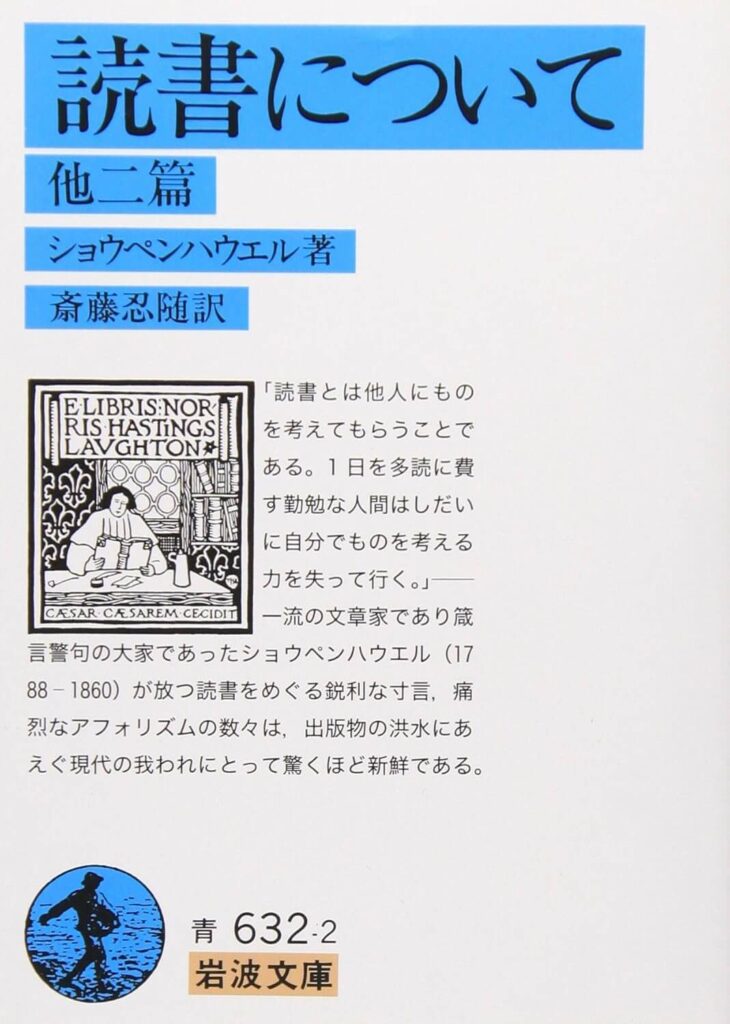
世間では「たくさんの本を読んでいる人が偉い」「速いスピードで本を理解できる人が優れている」などと考えられているように見受けられますが、ショウペンハウエルの金言の断片に心が救われる人も少なくないと思います。多くの本を速く読むよりも、分量的には寡少でも自身のペースでゆっくりと齝むように読む。
もしかすると、こうした遅読こそが、とりわけインターネット上で膨大な情報にいつも晒され続けている私たちに必要な、読書に対する正しい態度かもしれません。これは『論語』に出てくる「學びて思はざれば則ち罔し。思ひて學ばざれば則ち殆し」という一節とも部分的にリンクします。
背表紙を読むだけでも立派な読書
さらに言えば、背表紙を読むだけでも立派な読書です。私は学生時代、大学図書館の韓国語書籍のコーナーに行って、よく背表紙を読んでいました。「背表紙の読書」です。まだ本一冊を読み通せるほどの韓国語の膂力がない頃でしたが、背表紙だけなら読める。そして、知らない単語が目についたら、すぐに調べて覚える。
例えば、말뚝《杭》や길손《旅人》などといった単語は「背表紙の読書」をしながら覚えたことばです(韓国文学に詳しい方であれば何の本か想像がつくでしょう)。日本語書籍についても、どんな本があるのか、どんな書き手がいるのかを知るのは大事な勉強で、「背表紙の読書」はある種の「教養的なるもの」を形成するのに役立ちます。
詩人の管啓次郎氏が言うように、本に「冊」という単位はなく、すべての本は緩やかに繋がっています。そのことを実感するためにも、書かれた言語を問わず、書架に連なる背表紙を見霽かすことは知的に意味のある営為なのです。
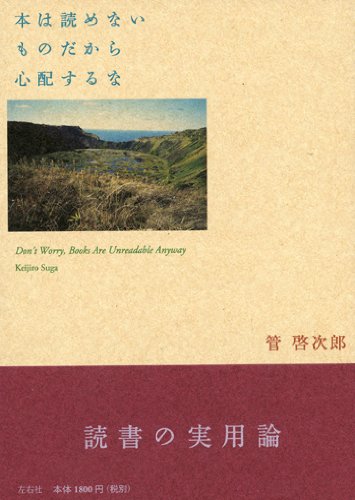
昨今のK-BOOKブームによって韓国語書籍が数多く邦訳され、日本語で同時代の韓国の文学や知の世界に接近できるようになりました。つまり、まずは日本語で味読した上で原書に挑戦することが可能な、韓国語学習者にとっては夢のような時代が到来したということです。
同じ本を別の言語で再度賞翫できる。これほど贅沢なことはありません。いつかきっと読めるはずの自分を信じて、原書もぜひ手にしてみましょう。構え過ぎず、まずは軽やかに「背表紙の読書」からいかがでしょうか。
ということで、今回も最後まで聞いてくださり、ありがとうございました。辻野裕紀でした。
オンライン書店で購入する